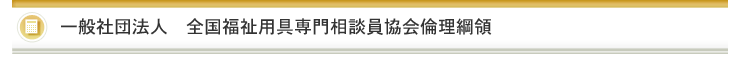わたくしたち福祉用具専門相談員は、高齢者、障害者、その家族等の方々(以下「利用者等」という。)が、福祉用具を利用される際に、福祉用具にかかる専門的知識、技術等をもって相談援助、適合等を行うとともに、福祉用具の導入後も適切な利用についてサポートする専門職です。
介護保険のスタートとともに福祉用具サービスが制度に位置づけられましたことから、その利用は順調に拡大していますが、少子高齢化に伴う社会的な介護力の低下や介護ニーズの多様化に伴って福祉用具の必要性が高まり、それに関わる福祉用具専門相談員の職務領域も急速に広がりを見せており、その役割と責任は益々重要性を増しています。
福祉用具専門相談員は、このような社会的な要請に応えるために、福祉用具の利用者等の尊厳を重んじ、住みなれた地域や環境で、自立した生活を支援するための最適な福祉用具サービスの提供に努める必要があります。
全国福祉用具専門相談員協会では、ここに「福祉用具専門相談員の倫理綱領」を定めて、福祉用具の専門職としての立場を明確にし、会員一人ひとりがこれを遵守し、自らの専門性を高めて福祉用具サービスの提供に努めていくものとします。
- 1.法令遵守
-
福祉用具専門相談員は、福祉用具サービスの提供において、法令等を遵守しなければならない。
- 2.平等原則
-
福祉用具専門相談員は、人の尊厳を守り、人種、性別、思想、信条、社会的身分、門地等によって差別してはならない。
- 3.守秘義務
-
(1) 福祉用具専門相談員は、利用者等から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。
(2) 福祉用具専門相談員は、業務上で利用者等の個人情報を用いる場合は、あらかじめ同意を得なければならない。
(3) 福祉用具専門相談員は、業務上で知りえた利用者等の個人情報については、業務を退いた後もその秘密を保持する。
- 4.説明責任
-
福祉用具専門相談員は、福祉用具の利用者等が福祉用具を利用する際に必要となる情報を、分かりやすい表現や方法等を用いて提供し、同意を得なければならない。
- 5.不当な報酬・利益供与の禁止
-
福祉用具専門相談員は、福祉用具の利用者等から不当な報酬を得てはならない。また、関係者に対して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
- 6.利用者情報の活用
-
福祉用具専門相談員は、福祉用具の利用者等とのコミュニケーションを重視して、福祉用具に関わる要望や苦情等の情報を理解するとともに、今後の福祉用具の適正な使用や開発等に有効に活用するよう努める。
- 7.多職種との連携
-
福祉用具専門相談員は、福祉用具の利用者等に質の高い福祉用具サービスを総合的に提供していくため、福祉、保健、医療、その他関連する専門職と連携を深めることに努める。
- 8.普及・啓発
-
福祉用具専門相談員は、常に福祉用具に係る調査・研究や普及・啓発に心掛けるとともに、利用者等に対して利便性の高い福祉用具サービスの提供に努める。
- 9.専門性の向上
-
福祉用具専門相談員は、常に福祉用具の専門的な知識・技術等の研鑽に励むとともに、後進を育成し、専門職としての社会的信用を高めるよう努める。
- 10.社会貢献
-
福祉用具専門相談員は、常に福祉用具サービスの充実を図るとともに、利用者等に対し自己及び所属する組織がもつ知識、技術等を積極的に提供して社会貢献に努める。